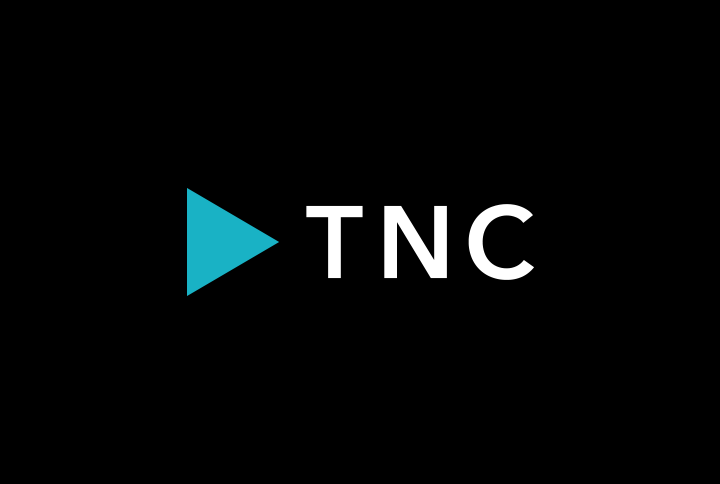
【第6回大島渚監督『青春残酷物語』】
火曜日の中川龍太郎です。
毎週この記事を書く度に思うのですが、皆様はどんな時間帯にこれを読まれるのでしょうか。僕は他のメンバーが更新するとすぐにチェックします。まあ近しい人たちなんで関心があるわけです。
学生でしたら、水曜日の2限が退屈な講義の人の方が僕の記事を最後まで読んでくださる率が上がるのではないでしょうか。社会人の方でしたら…会社に行く途中の満員電車でスマートフォンを取り出して、写真の掲載もない、延々と文字で埋め尽くされた僕の記事を読みたいかどうか…相当怪しいですよね。因みに、自分は一応映画を撮る側ですので、映画を評論するつもりはありませんし、そんなことが自分の能力でできるとも思っていません。僕にだって敬愛している偉大な評論家の方は沢山いますので、軽はずみに映画についてあれこれ「評論」などはしたくありません。ただ、一人の大の映画ファンとして、好きな映画を賛美しまくるってスタンスで書いています。そんでもって、できたら観てみてください…(小声)という感じですかね。
そろそろ我らが日本の「青春映画」について書きます。
前々回の『灰とダイヤモンド』と少し通じるところ(あくまで一種の気分として)もあるかもしれませんが、大島渚監督の『青春残酷物語』。
中学時代に観て、強烈なショックを受けました(ませたガキですよね)。
見るからに不貞腐れた若いチンピラが出てきます。繁華街を歩く、これまた見るからに不貞腐れた女の子を強引にナンパします。二人は結託して美人局を行いはじめます。そして二人は引きつけあいながら、当然のように遠ざけあってもいきます。二人はまるで何かに復讐するかのように美人局をするんです。暴力にしても売春にしても、同じように復讐なんだ、反発なんだ、そんな匂いが強烈に漂ってくる映画です。この手の映画の常として、二人は身を滅ぼしていき、最後は悲惨な末路を辿ります。
この映画は学生運動の弟世代の物語なんでしょうか。戦争を知る「大人」世代。学生運動で自由を求めて戦いながら挫折した「兄姉」世代。そして自由を持て余して、行き場を失った閉塞感に苛まれる「主人公たち二人」の世代。おそらく僕たちの世代はこの主人公たちの世代が延々と気だるく持続しているような感じなのでしょうか。
成長を描く青春映画は数多あります。しかし、多くの青春は大なり小なり挫折した残骸のようなものを引きずっているのではないでしょうか。大島渚はそれまで明るく夢のある青春映画を描いてきた日本映画の美しい系譜の中に、突如この暴力的な青春をぶちこみました。僕はその時代を生きていませんので完全な推測になりますが、リアルタイムでこの映画を観た人たちは「映画でこんなことを描いて良いのか!?」っていう衝撃が凄まじかったんじゃないかと思います。おそらくその当時、映画という存在はいくつかのジャンルに区分された娯楽作品と同義語だった。そこに大島渚は強烈な自分の怒りを、哀しみを、絶望を、どろどろした性を、他者に対する不信感を、ぶつけたって良いんだ、いや、それこそがこれからの新しい映画なんだぞ!って意気込みで『青春残酷物語』を世に放った。ロックみたいなもんなんですかね。これぞロックっぽい感じがしますよね。
大島渚のやった「こんな映画ってあり!?」感を、フランスではゴダールやトリュフォーを旗手とした若者たちがどんどん撮り始めます。それが世界的なムーブメントになって、有名な「ヌーヴェルバーグ」と言われるわけですね。ゴダールもトリュフォーも確かに素晴らしい。でも僕個人にとっての「ヌーヴェルバーグ」ってものは大島渚なんじゃないかと感じます。『勝手にしやがれ』のような独自のユーモアやスタイルの斬新さはありません。『大人は判ってくれない』のような高いセンスに裏打ちされたドライな悲哀もないかもしれません。ただそこには不器用なまでの怒りが満ち溢れている、それが『青春残酷物語』なんです。倫理をすっ飛ばして「俺は怒っているんだ!」と叫ぶ姿は清々しいです。露悪的な青春だってあるわけです。事実、中二病真っ盛りだった僕は大島渚の映画に触れたことで映画というものに本格的に傾倒していきます。
政治というアプローチによって描かれている部分も多いので、現在の目から見るといささか実感のわきにくいところもあるかもしれません。ただ、怒っているという感情を描く映画なんだと思って観れば、かなりの共感を今でも得られる作品だと思います。若い人たちは特に。青春を描く日本映画というと、「モテないダメ男」について描いた青春映画が最近メジャーでもインディーズでも多いように感じます。それ自体は面白い作品も多いですし、今という時代を切りとっている側面もあるでしょう。監督自身の個人的な実感に裏付けされた素晴らしい作品も沢山あります。ただ、そういう映画が続いてくると、「それだけなの?」と毒づきたくなってしまう、生意気な自分もいます。僕にとって「挫折した青春」といえば、最近数多制作されている「童貞モノ」(一概に括れるわけじゃありませんし、失礼な書き方だとは思いますが許して下さい)じゃなくて、大島渚の『青春残酷物語』の方が、しっくりきます。これは完全に趣味の違い、感覚や経験の違いなんでしょうが。
現在は簡単に怒ることが容易ではなくなっている時代なのかもしれません。僕もなるべくなる特定の何かを名指しして批判することを避けるように心がけています。それは批判が返ってくることが怖いからではありません。何かを強く批判することで見失ってしまう何かが自分の中にはあるからです。
それでも、自分が何に怒っているか、どう怒っていて、どう許せなくて、どうしたら自分なりに落とし前をつけたら良いのか、それはこれから映画を通して表明しつづけていくんじゃないかと思います。どんな形式をとるにせよ、どんな題材を選ぶにせよ、怒りと哀しみは絶対に画面に小さくても映り込んでいるはずです。
最後に。
僕は大島渚監督をとても尊敬しています。
今年公開の新作『Plastic Love Story』のシナリオの改訂作業中に大島渚監督の訃報を知りました。しばし言葉が出てこなくて、自分の中で小さいけれど確かに何かが終わり、これから自分が何者かにならなくてはならないんだって、少しだけ感じました。
大島渚の死は、僕の青春の代名詞ともいえる親友がメールで伝えてくれました。その時、僕は自分の青春時代の象徴ともいえる新宿のルノアールにいました。そして、その時、一緒にいて編集作業を共にしていた方は、僕が高校時代に詩集の出版をした時から編集者としてお世話になってきた方で、大島監督について何度も話したことがある人でした。青春を甘えのことだと仮定するならば(僕はあまりそう思わないのですが)、今こそ自分の青春を終わりにするのに最高のタイミングだなと勝手に考えてしまいました。
大変に個人的な話を失礼しました。しかし、素晴らしい創り手は、その死によってもなお、多くの名もない誰かに「個人的に特別な体験」を残していくのだなと思いました。そして、こればかりは自己満足なんでしょうけど、僕としては、その時に一生懸命創ろうとしていた『Plastic Love Story』を大島監督に言い訳なしで観てもらえるような作品にしようと誓いました。
ちょっと大袈裟で、こっぱずかしいお話ではありましたが、後日慌ててこの記事を消す!ってことにならないように日々精進していく所存です。
中川龍太郎





