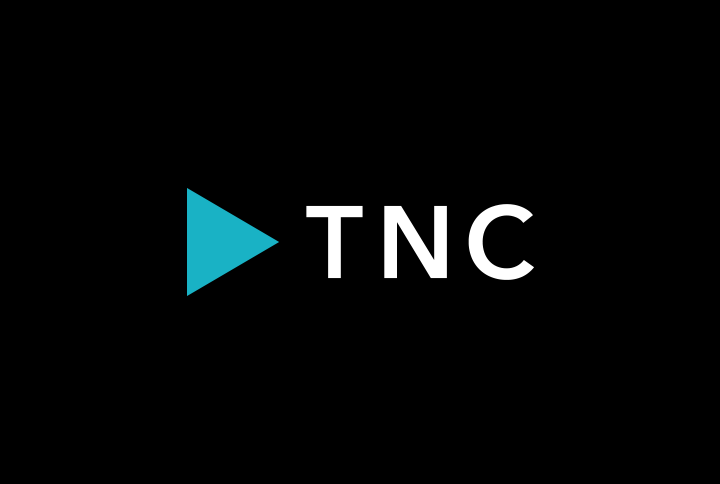
【第3回『汚れた血』レオス・カラックス監督】
火曜日は中川の日です。
先週は初のコメントをいただきまして、大変ありがたかったです。このブログも誰かしらが読んでくださっているのだと思うと、非常に勇気づけられると同時に、ちょっと緊張してきますね。今日も先週・先々週と同じ流れで「青春映画」。
僕が幸運にも世界のナカガワになったら「最も影響を受けた監督は?」という質問を繰り返し浴びせられて、その度に僕は「レオス・カラックスさんです」と答え続ける気がします。それくらい影響を受けた監督で、この監督の作品と出会っていなかったら、僕はここまで映画に熱狂してきたか怪しいとさえ思います。
『青春群像』や『オルエットの方へ』が集団の中で感じる孤独こそ描かれているものの、基本的には友人たちに囲まれた青春をリアリスティックに切りとっているのに対して、『汚れた血』は「僕」と「彼女」しかほぼない主人公の孤独すぎる青春がファンタジックに紡がれていきます。
まず何が素晴らしいって、主人公のアレックスがおそらく年上のお姉さんと思しきアンナという名を借りたジュリエット・ビノシュに振られ続けるところです。監督自身を投影しまくってる感じ全開のアレックスが、全編を通してこれでもかというほどアンナさんに好き好き言い続けて、徹底的に流され続けます(妙にリアルに生々しくスルーしていくので見ようによってはちょっと笑えます)。若さとは満ち足りなさのことであり、その満ち足りなさを受け入れることができない時期のことなんだと思います。そのことを証明するかのように、世界の男たちを代表して、アレックスはアンナに振られ続けるんです。
次にこの映画は「疾走」について扱っているところが素晴らしいと思います。走ることについての映画。映画は誕生以来、運動を捉えることを至上の喜びとしてきたんだとよく言われます。確かに走っているシーンはその映画がいかにちょっと…ってものでも無条件で気持ち良いことがありますよね。ジョン・フォードにしても黒澤明にしても、馬の疾走を基調とした、運動を描く天才だったからこそ、広く大衆に受け入れられたのだと思います。カラックスは疾走を若さの一部として切りとります。若さとは、走り出すことと泣きだすことが矛盾せずに共存する、人生における稀有な一時期なんだと思います。主人公はその高揚感と不安に押しつぶされそうな閉塞感を、ただただ走るだけの姿で矛盾なく描きだします。
『汚れた血』は細部という細部まで丹念に練り上げられています。ありとあらゆることが素晴らしすぎて上手くまとめることが難しいのですが、最後にもう一つ、この映画の圧倒的な美点を挙げてみます。泣いているアンナを笑わせようとするアレックスの姿に象徴される、「笑顔を引きだそうとする」というモチーフ。これには心底打ちのめされた記憶があります。泣いているアンナに手品をしてみせるアレックス。それに対していちいち天使のような反応を見せるアンナ。それでも心の距離が近づくことはない。いや、一瞬近づいたように見えるんだけど、結局同じような場所に戻っていく。そこで紡がれるショットの連続には、サイレント映画のような魅力が溢れています。しっかりと視覚によって、とても繊細に二人の距離が提示されていくんです。
それにしても、この映画を見ているといつも思うことなのですが、『汚れた血』のビノシュって女子受けが物凄く悪そうですよね。同性の友達がいなそう…。ま、いかにも女子受け悪そうな子に熱を上げるあたりも若さの特権ということなのでしょうか。
カラックスはこの後も『ポンヌフの恋人』『ポーラX』と、これまた傑出した青春にまつわる映画を撮ります。『汚れた血』の前作『ボーイ・ミーツ・ガール』も素晴らしいです。その全てが若さの痛みを克明にフィルムに焼き付けています。
『汚れた血』から26年経って、現在公開中の新作『ホーリー・モーターズ』で、カラックスは初めて「若さ」を映画で追いかけまわすことをやめたようにも感じます。カラックスももう50歳をすぎて(確か自分の父と同い年です)、さすがに若さにばかり固執していられなくなったのでしょうか。作中、「かつてそこにあった若さ」というかたちで若さについての言及がなされていますが、そこにあるものは絶え間ない疲労であって、徒労感であって、目の前で疾走するかつての若さは面影もありません。逆に斬新で胸を突く徒労感の表現が、観客の目と耳と心を奪います。
『ホーリー・モーターズ』で描かれている「自分が自分であることに対する疲れ」は若い時に思いっきり自意識過剰な映画を撮りきっていたからこそ出てきたものなのかもしれません。
やはり、僕が『汚れた血』の魅力を語ることは難しかったようです。僕の語彙力ではこの映画の激しさと美しさの一端にさえ触れることができない気がします。言葉では絶対に表現できないと思わせてしまうのだから、やはり映画として素晴らしいということなんだと思います。それでもカラックスさんに大変申し訳ないし、カラックスに熱狂してきた自分自身にも申し訳ない記事になってしまったかもしれません。
万が一、僕たちの映画が大ヒットして、大監督になってしまって、ここで書き連ねられたブログが文庫化されるような嬉しい事態が起きてしまったら、僕は真っ先に今日の記事をリライトすることになるでしょう。ですので、この記事はレアものです。そして出版関係のお仕事に従事されている方がご覧になっていましたら、いつでもご連絡ください。前倒しして何本でも記事を書きますんで(その前にもうちょっと名前が知られるようにならなくちゃなりませんかね)。
中川龍太郎






