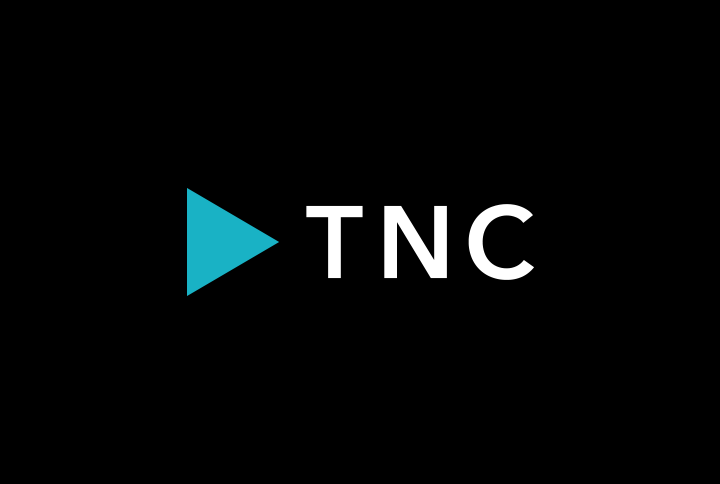
父殺しの物語
こんにちは。武笠恭太です。
6月に入りましたね。6月というと、「父の日」があります。
今日は、少々時期が早いですが、「父の日」になぞらえて、父親を扱った映画を一本ご紹介したいと思います。ご紹介するとは言っても、皆さんもご存知かと思われる映画ですが、スタジオジブリ作品の『ゲド戦記』(宮崎吾朗監督、2006年)です。この作品、僕大好きなのです。
物語のあらすじを簡潔にまとめると、一国の王子である主人公アレンが父王を殺すところに端を発し、国を抜け出した彼が大賢人ゲドとともに旅をし、その旅の中で、均衡が崩れた世界とアレン自身がもつ内面的な問題の両軸を解決する、という冒険ファンタジーになっています。
この作品は「父殺し」というのが一つの大きなテーマとなっています。
なぜアレンは、王である父を殺してしまったのか。
巷にある『ゲド戦記』に関する評論に目をやると、王=宮崎駿、アレン=宮崎吾朗という暗喩を引き合いに、息子の宮崎吾朗監督はアレンに自分を投影し、偉大なアニメーション監督である父を模した王を作品内で殺すことでもって、映画監督としての自立を目指した、というような内容が通説のようです。
確かに、こうした観点はなるほどと納得してしまいますが、このような外付けの動機を引き合いに出さなくとも、純粋に作品単体として、アレンがなぜ父を殺したかという理由に目を向けてみることに僕は関心がありました。
このことは作品内で明確にセリフでも映像でも語られていない(ように見える)ので、あくまで個人的な解釈の域を脱しないのですが、思うに、アレンにとって、王である父の存在は、「超えるべき壁」であったと思うのです。彼は王子として生まれたわけですから、いずれは父の王位を継承しなければいけない運命にあります。しかし、人々に信頼され、国を統べる立場にいる父に比べたら、自分自身はとても人の上に立てるような器ではない。常に孤独と死の恐怖に怯えて生きている。彼はそんな葛藤をもっています。そして、そうした弱さや不安のみが一人歩きし、それだけに心を囚われた彼の一つの人格が逆上して、無理矢理にも父を殺すことでもって、「父を超えた」という錯覚を自らに与え、急場しのぎの自慰を施した。
アレンの父殺しの動機の背後には、おそらくこのような論理が蠢いていたはずです。
しかし、アレンが犯した行動は、単に父という壁から逃避するための、その名の通りの物理的な親殺しであって、精神的に父を殺す行為ではありませんでした。父を殺すというのは、もちろんシンボリックな意味で、「超えるべき壁」としての父という存在を意識の上で乗り越えることであって、そこに彼は至らなかったというわけです。
それでも、物語が終盤に向かうにつれ、自分の弱さを自覚したアレンは、すでにこの世にはいない父の存在と初めて向き合うところで映画は幕を閉じます。今度は逃げも隠れもせずに。それはアレンの内部で、父親が真の意味で「壁」として立ち現れたことを意味しています。
『ゲド戦記』に見られるこのような父と子の物語というのは、古くから物語の類型となっていて、父と子の関係にとどまらず、師匠と弟子の物語なんかもそうです。周知の作品を一つ挙げれば、『明日のジョー』とかです。弟子にとって師匠は「殺しの対象」であり、逆に師匠は弟子に「殺される対象」である。上司と部下の物語、先生と生徒の物語などもそうかもしれません。教える側と教えられる側、「教育」の本質とは、常に闘争にあるのだと思います。
父の日から話が大幅に逸れてしまいましたが、いずれにせよ子である自分自身が父を超えることが最大の親孝行であると思います。
それではまた来週!
武笠恭太





